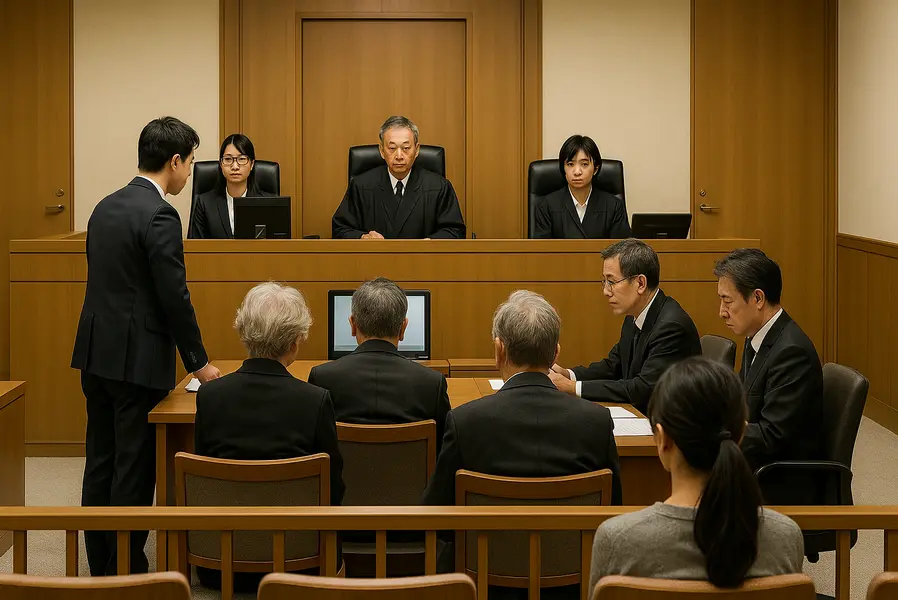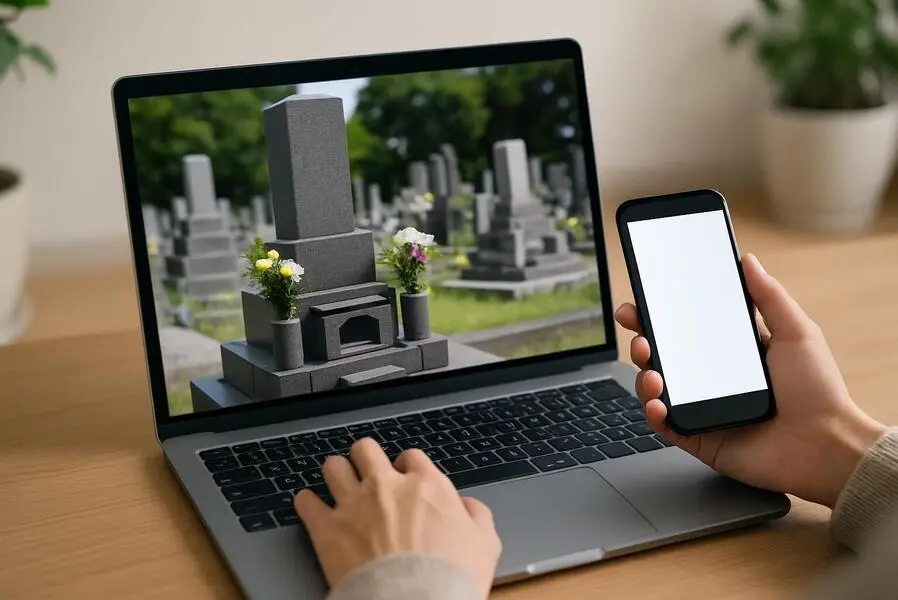盆踊りに集う夏の夜~先祖とつながるひととき
夏の夕方、まだ蒸し暑さの残る空気のなかで、どこか遠くから太鼓の音が聞こえてきます。盆踊りの季節が、今年もやってきました。
近所の公園では、やぐらを囲んで浴衣姿の人たちが輪になり、楽しそうに踊る姿をあちこちで見かけます。子どもたちは手拍子に合わせてステップを踏み、大人たちは笑いながら見守っています。夏の夜らしい、にぎやかでどこか安心できる光景です。
こうした盆踊りは、町内会の催しや地域のイベントとして各地で行われています。観光行事として大規模に開催されるものもあり、夜店の灯りに誘われてふらりと立ち寄ったり、SNSで話題の踊りを見に行ったりと、楽しみ方もさまざまです。
身近なお祭りとして親しまれている盆踊りですが、その由来や意味を知っている人は意外と少ないかもしれません。
もともとは、先祖の霊を迎えて供養するために行われてきた、宗教的な行事として始まったのです。
盆踊りの由来とは?~念仏踊りに始まる先祖供養の歴史と意味
盆踊りは、仏教行事である「盂蘭盆会(うらぼんえ)」を起源としています。盂蘭盆会とは、先祖の霊を迎えて供養するための行事で、現在のお盆(8月13日~16日頃)のもとになったものです。
関連記事:【2024年お盆の時期はいつ?~準備・お墓参りと海外リゾート散骨~】
この時期になると、多くの家庭では、迎え火を焚いて先祖の霊を迎え入れ、家族で過ごしたあと、送り火とともに見送るという習わしが続いてきました。先祖を敬う気持ちや、日々の暮らしの中で手を合わせる習慣は、ずっと昔から受け継がれてきたのです。
そうした供養の風習が定着していくなかで、信仰のあり方にも変化が起きていきます。とくに平安時代の終わりごろから、「南無阿弥陀仏」と唱えることで阿弥陀仏に救われ、死後に極楽浄土へ生まれ変わることができる「念仏信仰」が広まっていきました。この教えは、難しい仏教の経典を読んだり修行を積んだりすることができない庶民にとっても、口に出して唱えるだけで救いが得られるという、とてもわかりやすく親しみやすいものでした。そして、人々は、念仏を唱えるだけでなく、その想いを体を動かすことで表すようにもなり、念仏を唱えながら踊る「念仏踊り」が各地で行われるようになりました。
このように、仏への祈りとして始まった念仏唱和は、やがて踊りというかたちで親しまれるようになり、先祖を偲びながらみんなで心をひとつにする「盆踊り」へとつながっていったのです。そこには、「霊と一緒に踊る」と感覚も含まれていました。さらに、鎌倉時代の終わりから室町時代にかけて、踊りの形は少しずつ整い、地域ごとに独自のスタイルが生まれていきました。
こうして生まれた盆踊りは、先祖の霊を迎え、感謝の気持ちとともに手を合わせ、心を通わせる、日本らしい祈りのかたちとして、今も夏の夜に親しまれているのです。
日本三大盆踊りに込められた魅力と先祖供養の心~阿波踊り・郡上おどり・西馬音内盆踊り
この「霊と一緒に踊る」という考えは、今も各地で大切にされています。
たとえば徳島県の「阿波踊り」では、毎年8月のお盆の時期になると、街中が「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損々!」という掛け声でにぎわいます。
この言葉には、「見ているだけでなく、いっしょに踊ろうよ」という呼びかけが込められていますが、実はそれだけではありません。阿波踊りは、もともと盂蘭盆の夜に先祖を慰めるための踊りだったとも言われています。踊り手と観客が一体となって踊ることで、まるで先祖の霊と時を過ごしているような、供養の時間になっているのです。
また、岐阜県の「郡上おどり」も見逃せません。400年以上の歴史をもつこの盆踊りでは、7月中旬から9月初旬まで連日踊りが行われ、お盆の時期には「徹夜おどり」として、夜を通して踊る日もあります。郡上おどりも、先祖の霊を迎えて感謝を伝え、送り出すための踊りとして受け継がれてきました。町の人が一つの輪になって踊る様子は、地域が一体となって供養する姿そのものです。
さらに、秋田県の「西馬音内(にしもない)盆踊り」も印象的です。藍染めの端縫い衣装を着て、編み笠をかぶって顔を隠しながら踊る姿は、どこか霊そのもののように見えます。囃子も哀愁を帯びていて、幻想的な空気に包まれたその踊りには、亡くなった人の霊を静かに迎え、心を通わせようとする優しい祈りが感じられます。
このように、どの盆踊りにも、その土地ならではの供養のかたちがあり、霊と過ごすという気持ちが、今も大切にされています。

盆踊りに宿る祈り~静かな願いとともに踊る夏
現代の盆踊りは、お祭りや観光イベントとしての楽しさも大きな魅力になっています。屋台をのぞいたり、友人と浴衣で写真を撮ったり、SNSで話題の踊りを真似してみたりと、今の時代ならではの楽しみ方も広がっています。それでも、踊りの中心にはいつも、先祖の霊を迎えて一緒に過ごす時間への、静かな願いが込められているのかもしれません。
今でも、盆踊りの前後には迎え火や送り火を焚く風習が残っている地域もあります。「来てくれてありがとう」「また来年、会いましょう」と伝える想いが込められています。
そして、その間にある盆踊りは、にぎやかで楽しくありながら、どこか懐かしさや少しの切なさも感じられる時間です。ふと風が吹いたときや、どこからか懐かしいにおいがしたとき、「ああ、誰かが帰ってきているのかもしれない」と感じることもあるでしょう。踊ることは、声に出せない祈りや感謝を、体を通してそっと伝えることです。
いまを生きる私たちと、かつてこの世を生きた人たちが心を通わせる夏の夜が、盆踊りの中に今も静かに流れています。そんな優しさが、今年の夏も、どこかで人知れず灯り続けている気がします。