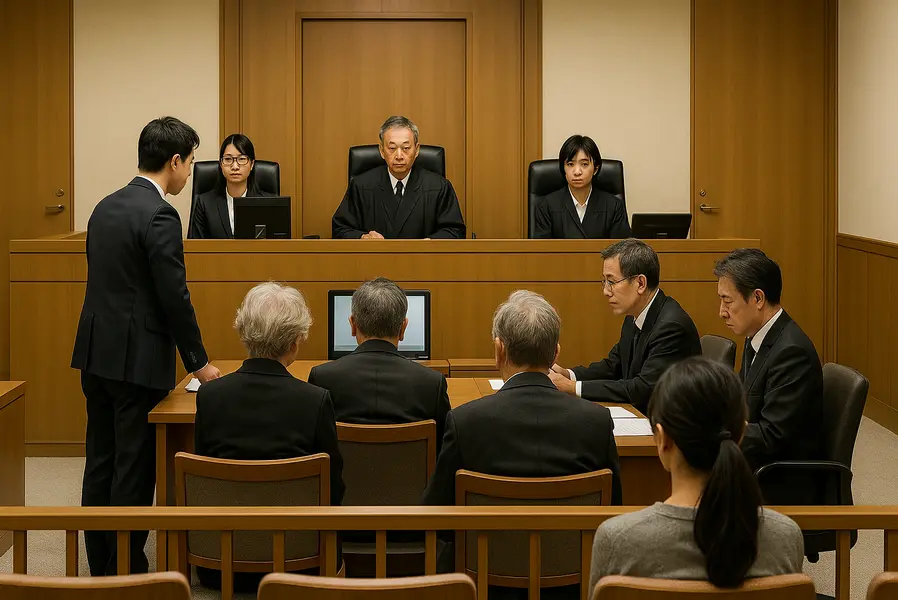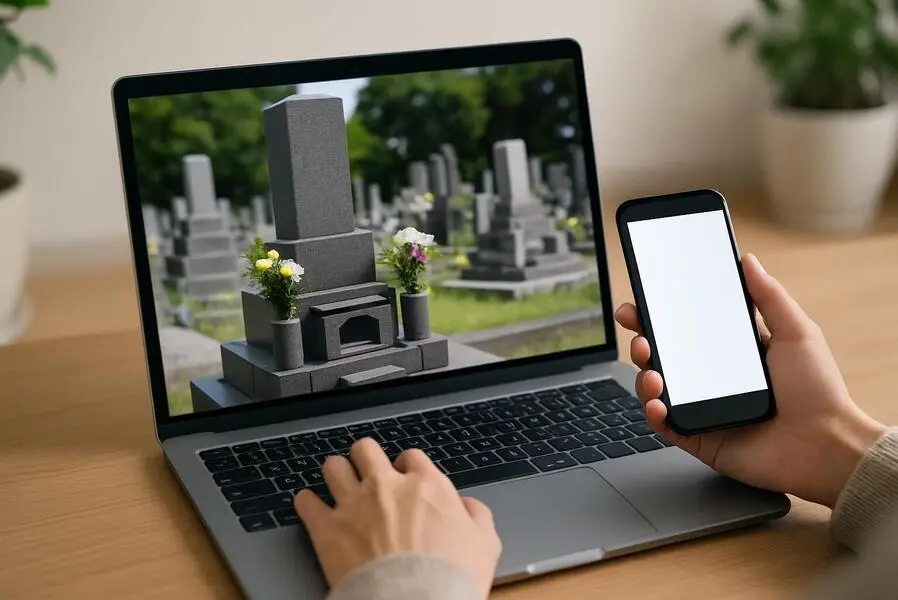日本の火葬率と都市部で深刻化する火葬場の混雑問題
日本では、葬儀のあとに火葬を行うのが一般的です。厚生労働省の統計によれば、近年は99%を超える方が火葬を選んでおり、世界的に見ても非常に高い割合となっています。
そのため、各地の火葬場は利用者が増え続け、特に都市部では人口が集中していることもあり、火葬場の混雑が深刻な課題となっています。
火葬は一度に行える件数が限られており、同時に複数を扱える施設であっても、炉の数や人員体制には制約があります。特に東京都や神奈川県など首都圏では、葬儀の日程は火葬場の予約状況に左右されやすく、希望日に利用できず数日待つことも少なくありません。また、友引明けの日や、仏滅を避けた吉日とされる日には予約が集中し、順番待ちがさらに長くなる傾向があります。
遺族にとって、大切な人を亡くした直後に数日間待たされるのは大きな負担です。自宅や安置施設での保管費用がかさむうえ、心情的にも区切りをつけられない時間が続いてしまいます。このような現状を受けて、火葬場を運営する自治体や指定管理者は、混雑を和らげ、待ち時間を減らすための工夫を進めています。
関連記事:【多死社会における火葬待ち問題】
関連記事:【火葬待ち問題の救世主「遺体ホテル」~高まる需要と残る課題~】
名古屋・八事斎場の拡充~火葬件数増加と待ち時間短縮
愛知県名古屋市の「八事斎場」では、2025年4月に第二斎場が完成し、火葬の件数を従来の約1.5倍に増やしました。新しく30基の火葬炉が設けられ、そのうち1基を予備炉としたことで、実際には29基が動いています。1炉につき1日3件の火葬を行い、元日以外の364日を稼働日としたことで、年間ではおよそ3万1,600件に対応できるようになりました。従来の約1万9,000件から大きく増え、市内の火葬需要を十分に支えられる規模となっています。
火葬炉の増設に合わせて、告別や収骨に使う部屋や待合室といった施設も増設されました。告別・収骨室は24室、有料待合室も24室用意され、以前よりも広く落ち着いた環境で見送りができるようになっています。待合室がより快適になり、火葬を待つ時間も落ち着いて過ごせるようになりました
この取り組みによって、市民は希望から1~2日以内に火葬を行えるようになり、繁忙期でも長く待たされることが少なくなりました。以前は数日から1週間近く待たされることもありましたが、今ではその時間が大幅に短縮されました。保管にかかる費用の心配も減り、遺族が気持ちを落ち着けて見送りの準備を進められるようになっています。
一方で、市にとっても業務を効率よく進められるようになり、将来増える火葬件数への備えも整いました。八事斎場の拡充は、市民と行政の双方にとって安心につながる大きな一歩といえます。

火葬場改善の効果~遺族の安心と多様な葬儀への対応
火葬場の体制を改善することで、遺族の負担は経済面でも心理面でも和らぎます。火葬を待つ間に必要な安置費用は、1日あたり数千円から1万円以上かかることもありますが、待ち日数が短くなればその分の費用が減り、負担が少なくなります。また、大切な人を亡くしてから何日も火葬を待つのは、遺族にとってつらい時間です。すぐに火葬できるようになれば、気持ちを整理しやすくなり、落ち着いて見送りの準備を進められるようになります。
さらに近年は、家族葬や直葬といったシンプルな葬儀が増えています。直葬は火葬を中心に行うため、予約が取れなければ全体の予定が崩れてしまいます。火葬の枠が増え、時間帯に幅ができれば、さまざまな葬儀の形にも無理なく対応できるようになります。
一方で課題も残ります。地方では人口減少の影響で火葬場が空いているところがあるのに対して、大都市では混雑が続いています。都市と地方で利用状況が大きく違うことが、これからの問題です。また、「午前中にしたい」という希望も多く、時間を分散させる取り組みを進めるには、遺族や葬儀社の理解が欠かせません。
多死社会に向けた火葬場のあり方と今後の課題
火葬場の体制も、時代に合わせて少しずつ見直されています。八事斎場のように炉や施設を拡充して待ち時間を減らす取り組みは、遺族が安心して見送れるようになるだけでなく、市の側にとっても将来の需要に備える大切な一歩となりました。こうした流れは一部の地域にとどまらず、今後さらに広がっていくと考えられます。
とはいえ、すべての課題が解決したわけではありません。都市と地方で利用状況に差があることや、午前中に火葬を希望する声が多いことなど、地域や利用者ごとに異なる課題が残されています。施設を増やすだけでなく、時間の分散や予約の仕組みなど、運営方法をどう柔軟に変えていくかも大きなテーマです。
これからの多死社会に向けて、火葬場のあり方をどう整えていくかは、自治体や葬儀社だけでなく、社会全体で考えるべきことです。待ち時間の短縮や環境の改善といった取り組みを積み重ねていくことが、遺族が心静かに大切な人を見送れる社会につながっていくでしょう。