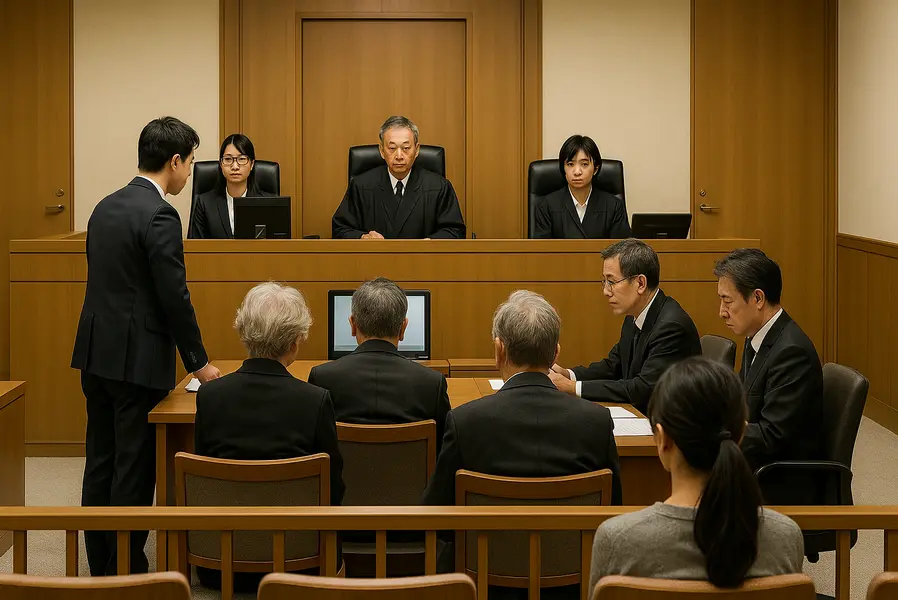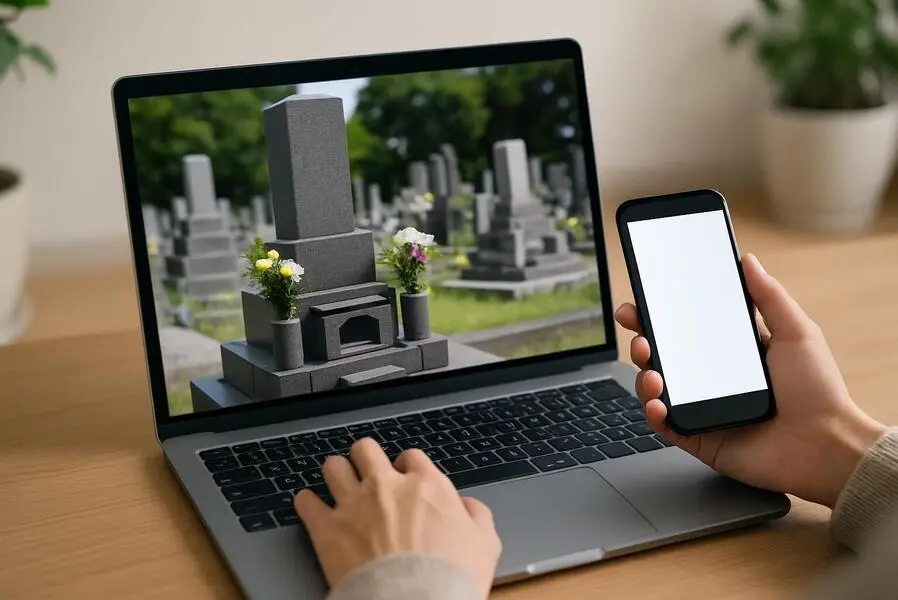エンディングノートの認知と実際の利用状況
「エンディングノート」は、今では終活の定番になっています。書店や文具店でも専用のノートが並び、テレビや新聞で紹介されることもあり、認知度はかなり高まっています。 しかし、「知っている」と「実際に書いている」には大きな差があります。
【終活白書2024(株式会社ニチリョク)】 によれば、エンディングノートを実際に書いている人は全体の42%にとどまり、半数以上はまだ手を付けていません。
さらに、内閣府が実施した【高齢者の生活と意識に関する国際比較調査(令和6年度)】では、エンディングノートやリビングウイルを実際に作成している高齢者は全体の約1割にとどまるという結果が出ています。
つまり多くの人が「必要だと感じながらも、実際には始められていない」状況です。
では、なぜ書けないのでしょうか。理由としてよく挙げられるのは、「まだ元気だから」「書くことに抵抗を感じる」「何から書き始めればいいか分からない」といった声です。大事だと思っていても、心の壁や実際の書きにくさがあり、多くの人がまだ踏み出せていません。
自治体と医療現場で進むエンディングノートの取り組み
そうした中で、各地の自治体や医療福祉の現場では少しずつ取り組みが進んでいます。
・三重県桑名市
「桑名市版エンディングノート」を作成し、介護高齢課や地域包括支援センターで無料配布しています。PDF版も公開されており、「全部を書かなくてもよい」「遺言のような法的効力はない」「定期的に見直すことが大切」といったガイドも添えられていて、気軽に書き始められる工夫がされています。
・静岡県富士宮市
「思いをつなぐノート 第2版」を発行しています。市民の声を取り入れて改訂されており、医療の希望や家族へのメッセージなどを自由に書き込めます。市役所や地域包括支援センター、交流センターや図書館で無料配布しているほか、PDF版も公開されています。
・大阪府八尾市
情報冊子「未来を描く心のノート」の中に、エンディングノート「わたしの人生の覚え書き~未来への手紙~」を収めて配布しています。市役所の高齢介護課や地域包括支援センター、社会福祉協議会で入手でき、電子版PDFも利用可能です。「最初からすべて書かなくてもよい」「定期的に見直すこと」「家族と共有すること」が推奨されており、書き方の相談窓口も案内されています。
・青森県青森市
「わたしノート」を作成し、高齢者支援課や地域包括支援センターなどで配布しています。公式サイトからPDFをダウンロードでき、記入時の注意事項や相談窓口の案内もあわせて掲載されています。更新日も明記されており、安心して利用できる仕組みになっています。
・岐阜県医師会(医療現場の取り組み)
「これからノート」を開発しました。これは在宅医療や人生会議(ACP)に活用しやすいように作られており、本人の希望を多職種で共有できるよう工夫されています。令和7年3月末に完成し、8,000部が印刷されて県内の医療機関や自治体に配布されています。さらに2025年8月には活用研修会が岐阜県医師会館で開催され、医療・介護従事者や行政職員が参加して具体的な使い方を学ぶ機会が設けられました。
エンディングノートが普及しにくい理由
エンディングノートの普及に向けた取り組みは各地で行われていますが、実際に広がっているかどうかは別の話です。そこにはいくつかの課題が影響しています。
・心理的な抵抗
自分の死や介護について考えるのは勇気が要ります。特にまだ働き盛りや健康な人にとっては、「わざわざ書かなくてもいいのでは」と考えるのも自然です。実際に書こうとすると「縁起でもない」と感じたり、「書いたら現実になるのでは」と不安になることもあります。
・共有や更新の難しさ
せっかくノートを書いても、家族に伝えずにしまい込んでしまったり、何年も更新せずに古いままになってしまうこともよくあります。家族に見せる勇気や定期的に見直すのはなかなか難しいものです。
・入手のしにくさ
自治体で配っていても、平日の昼間しか窓口が開いていないので取りに行けない人もいます。ネットからダウンロードできるとしても、パソコンやプリンターがなければ難しい場合もあります。「欲しい」と思っても、なかなか手に入れにくい人もいます。
・内容の曖昧さ
エンディングノートには医療のことや財産、葬儀の希望、連絡先などいろいろな項目があります。そのせいで「全部書かないといけないのかな」と迷ってしまう人もいます。「空白を残すのはよくないかも」と感じてしまい、書き始められないケースもあります。

家族を支えるエンディングノート~今からできる実践
こうした課題はあるものの、エンディングノートが持つ役割はとても大きなものです。
自分の想いや希望を書き残すことは、将来の医療や介護の場面で家族が迷わず判断できる助けになります。また、財産や連絡先を整理しておけば、残された家族の負担を大きく減らすことにもつながります。
さらに、スマホやインターネットのアカウント、サブスクリプションの解約情報を書き残しておくことも欠かせません。契約やログイン情報は本人しか把握していない場合が多く、放置すれば費用が発生し続けたり、個人情報が残ってしまう危険があります。そして、放置された情報や契約の整理は、家族に大きな負担を与えることになります。
関連記事:【エンディングノートで遺族をサポートしよう~故人のスマホ・サブスクの解約手続き~】
最近では、紙のノートだけでなく、声や映像をデジタルで残せる「Memory Container™」のようなサービスも登場しています。書くことが負担に感じる人でも、自分の声で想いを残すことができ、更新や保存も簡単です。こうした仕組みが広がることで、エンディングノートはより多くの人にとって身近なものになりつつあります。
関連記事:【NTTデータが届ける「Memory Container™」~声と映像をクラウドに残す、新しいエンディングノート~】
エンディングノートは、思いついたことから少しずつ書き留めていくだけでも十分です。大切なのは、自分の意思を形にして残しておくことです。難しく考えずに、まずは一行からでも書き始めてみましょう。その一歩が未来の安心につながります。